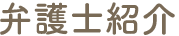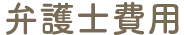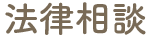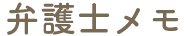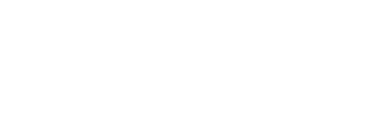
【裁判・建築】耐震偽装マンションにつき、建築確認を行った市に対する損害賠償請求を認めた裁判例(静岡地裁H24・12・7)
本件は耐震偽装マンションに関する事案で、構造計算業務に関与したものらへの責任も認められています(金9億5600万円ほど)。論点は多岐にわたりますが、建築確認を行った静岡市の責任が認められている点に大きな特色があります(金6億7000万円ほど)。
建築主事・静岡市の義務違反認定の基礎は次のような点にあるようです。
すなわち、本件は、建築主事が、構造計算書の2次設計結論部分が抜けていることに気づき、これの追完を指示したところ、後日申請者が最終ページのみを持参したが、建築主事は、その際に、「連続性について単に利用者番号、ソフトのバージョン番号、頁数を確認したのみで、九六頁、九七頁に記載されていた本件建物の各階におけるX方向の壁せん断力の数値と追完された最終頁(九八頁)に記載されている同数値が一致していることを確認しなかったものである。」とされています。その他、建築基準法の趣旨、本件建築主事の能力等もあわせて、義務違反が認定されました。
具体的な義務違反認定の際の視点として参考になると思われます。なお、本件は分譲会社が購入者(消費者)からの買い戻しに応じたうえ、分譲会社が原告となって提起した訴訟のようであり、耐震偽装発覚後の分譲会社のあるべき姿(とるべき対応)としても参考になると思われます。
判決文は、判例時報2173号62頁(上記部分は105頁以下)に掲載されています。
【民事・マンション騒音】階上の騒音につき差し止め・賠償を認めた裁判例(東京地裁H24・3・15)
マンション上下階における騒音問題につき、上階の者に対し、午後9時から翌日午前7時までの時間帯は40dBを超える騒音を、午前7時から同日午後9時までの間は53dBを超える騒音を、下階の部屋に聞こえるようにしてはならないこと、及び慰謝料・治療費・騒音測定費用の賠償を命じたものです(東京地裁H24・3・15 判例時報2155号71頁)。
騒音による損害賠償を認める事案も多いとはいえませんが、さらに差し止めを認める例は多くはなく(認めたものとして横浜地裁S56・2・18 判例時報1005号158頁)、騒音立証の方法も含め、実務上参考になると思われます。
扶養的財産分与として、夫マンションにつき、妻への賃貸を命ずる判決(名古屋高裁H21・5・28)
夫から妻に対する離婚等請求事件において、夫婦共有財産であるマンションにつき、清算的財産分与として、夫持分(8割程度)は夫が取得するとした上、扶養的財産分与として、「夫は妻に対し同マンションを賃貸せよ」との判決が出されました(判例時報2069号50頁)。離婚に伴う財産分与として実務上も参考になると思われます。
耐震偽装マンション、販売業者の代金返還義務を認める判決(札幌地裁H22・4・22)います。会社住友taisinn
札幌地裁は、平成22年4月22日、耐震偽装マンションにつき、購入者の錯誤主張に基づき、「耐震強度などの基本的性能は購入の重要な動機。誤解に基づき合意した売買は無効であり、被告は代金を返還する責任を負う」として、販売業者である住友不動産に対し、総額約3億7千万円の返還を命じる判断を示しました。耐震偽装の一番の被害者は購入者ら消費者であり、被害救済がすすむことが期待されます。
地元・北海道新聞の記事です↓。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/227480.html
耐震偽装マンションは無価値とする判決(札幌地裁H21・10・29)
札幌地裁は、平成21年10月29日、いわゆる耐震偽装マンションにつき、補修や再分譲・賃貸するとしても費用回収は容易ではなく、「実質的に無価値」と判断しました(判例時報2064号83頁)。
事案は、販売者デベロッパーと設計・監理者との間の紛争ですが、耐震偽装被害の一般消費者の方々の被害救済にも参考となる裁判例でしょう。
マンション建築差し止め決定(神戸地裁尼崎支部H22・2・24)
神戸地裁尼崎支部において、平成22年2月24日付けで、マンション建築差し止めの決定が出されていたとの報道がありました。
http://news.goo.ne.jp/article/kobe/region/T20100324MS01664A.html
行政上のルールを守ることが、近隣住民の権利(日照権・私法上の権利)の侵害までも許すものでないことを改めて確認する意義ある判断と思われます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792