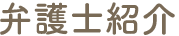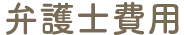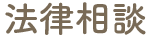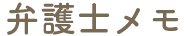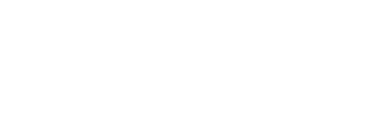
【裁判・民事】弁護士が不動産の売買による所有権移転登記手続について、売主側から依頼を受けていたところ、買主に対し、偽造された住民基本台帳カード等をもとに売主についての誤った本人確認情報を提供したことについて、弁護士の不法行為責任を認めた事例(東京地裁H28・11・29)
判例時報2343号78頁に掲載されています。
過失相殺が4割とされていますが、1億6000万円超の賠償が命じられています。
判決では、「証拠(乙2)によれば、自称Cが提出した本件遺産分割協議書の記載内容は、Iの死亡日が「平成44年9月17日」とされていること、相続開始日と被相続人の死亡日が異なっていること、上記相続開始日及び被相続人の死亡日がいずれも本件不動産の登記事項証明書に示された相続開始日(すなわち被相続人の死亡日)と異なっているという明らかに誤った内容を含むものであり(認定事実(11)エ)、遺産分割協議の内容を正確に示すものではなく、そのままでは遺産分割協議に基づく登記申請に用いることができないことを容易に気付くことができる内容のものである。」とされています。
事案としては賠償を命じられるものと思いますが、弁護士業務遂行として留意すべき事項も少なくいないと思われます。
【裁判・民事】自動車売買につき、所有権留保・販売会社名義の登録がされて、保証人が弁済した後、自動車買主の破産手続開始となった場合、その時点で販売会社名義の登録があれば、保証人は別除権行使ができるとする最高裁判例(H29・12・7)
最高裁平成29年12月12日(最高裁HP、金融・商事判例1533号36頁)は、「自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ、売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後、購入者の破産手続が開始した場合において、その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは、保証人は、上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができるものと解するのが相当である。」「その理由は、以下のとおりである。保証人は、主債務である売買代金債務の弁済をするについて正当な利益を有しており、代位弁済によって購入者に対して取得する求償権を確保するために、弁済によって消滅するはずの販売会社の購入者に対する売買代金債権及びこれを担保するため留保された所有権(以下「留保所有権」という。)を法律上当然に取得し、求償権の範囲内で売買代金債権及び留保所有権を行使することが認められている(民法500条、501条)。そして、購入者の破産手続開始の時点において販売会社を所有者とする登録がされている自動車については、所有権が留保されていることは予測し得るというべきであるから、留保所有権の存在を前提として破産財団が構成されることによって、破産債権者に対する不測の影響が生ずることはない。そうすると、保証人は、自動車につき保証人を所有者とする登録なくして、販売会社から法定代位により取得した留保所有権を別除権として行使することができるものというべきである。」と判示しました。
破産関係の実務においてよく見られる事案であり、重要な判断と思われます。
【裁判・民事】仲裁法18条4項の「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」に関する解釈・要件を判示した最高裁判例(H29・12・12)
最高裁平成29年12月12日(最高裁HP、金融・商事判例1533号28頁)は、「仲裁人は、仲裁手続の進行中、当事者に対し、法18条4項の事実の全部を遅滞なく開示すべき義務を負う(法18条4項)。その趣旨は、仲裁人に、忌避の事由である「仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由」(同条1項2号)に当たる事実よりも広く事実を開示させて、当事者が忌避の申立てを的確に行うことができるようにすることにより、仲裁人の忌避の制度の実効性を担保しようとしたことにあると解される。仲裁人は、法18条4項の事実が「既に開示したもの」に当たれば、当該事実につき改めて開示すべき義務を負わないが(同条4項括弧書)、仲裁人が当事者に対して法18条4項の事実が生ずる可能性があることを抽象的に述べたというだけで上記の「既に開示した」ものとして扱われるとすれば、当事者が具体的な事実に基づいて忌避の申立てを的確に行うことができなくなり、仲裁人の忌避の制度の実効性を担保しようとした同項の趣旨が没却されかねず、相当ではない。
したがって、仲裁人が当事者に対して法18条4項の事実が生ずる可能性があることを抽象的に述べたことは、同項にいう「既に開示した」ことには当たらないと解するのが相当である。」「仲裁人が、当事者に対して法18条4項の事実を開示しなかったことについて、同項所定の開示すべき義務に違反したというためには、仲裁手続が終了するまでの間に、仲裁人が当該事実を認識していたか、仲裁人が合理的な範囲の調査を行うことによって当該事実が通常判明し得たことが必要であると解するのが相当である。」と判示しました。
仲裁法18条4項につき、関係者の忌避申立の機会を確保するという趣旨から解釈・要件を明確にしたもので、仲裁のみならず裁判外紛争手続などにも参考になる重要な判例と思われます。
(忌避の原因等)
第十八条
当事者は、仲裁人に次に掲げる事由があるときは、当該仲裁人を忌避することができる。
一 当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないとき。
二 仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。
2 仲裁人を選任し、又は当該仲裁人の選任について推薦その他これに類する関与をした当事者は、当該選任後に知った事由を忌避の原因とする場合に限り、当該仲裁人を忌避することができる。
3 仲裁人への就任の依頼を受けてその交渉に応じようとする者は、当該依頼をした者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示しなければならない。
4 仲裁人は、仲裁手続の進行中、当事者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実(既に開示したものを除く。)の全部を遅滞なく開示しなければならない。
【裁判・民事】隣家の外壁塗装等にあたって、工事担当者に対し、化学物質過敏症にり患している旨説明していたにも関わらず、事前通告なしに薬剤散布したことに過失があるとされた事例(佐賀地判H28・10・18)
判例時報2347号122頁に掲載されています。
個別具体的な関係における業者側の注意義務を把握するものとして、被害救済に参考になるものです。
【裁判・民事】バイク転倒事故の原因が製造物責任法上の欠陥にあたるとして輸入業者に賠償を命じるとともに、業者から出版社への情報提供者に対する損害賠償請求を排斥した事案(東京地裁H28・9・28)
判例タイムズ1440号213頁以下に掲載されています。
製造物責任法の適用事例として参考になるとともに、業者から被害者に対する威嚇的訴訟(いわゆるスラップ訴訟)について、「一般に、雑誌の記事の編集権は当該雑誌の出版社にあり、出版社は、その責任と権限において、種々の取材を行った上、事実を取捨選択して記事の内容を構成し、これを雑誌に掲載するものであるから,出版社に対して他人の名誉等を毀損する情報を提供した者は、自己の提供した情報がそのままの形で記事として掲載されることは予見していないのが通常であることから,情報提供者の名誉毀損を主張する者において,情報提供者が自己の提供した情報がそのままの形で記事として掲載されることを予見していたことを示す特段の事情を立証しなければならないものと解するのが相当である。またこの点からすれば,少なくとも情報提供行為との相当因果関係が肯定されない限り,他人の名誉等を毀損する記事等の掲載について情報提供者が教唆幇助を含む共同不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。」と判示して業者の威嚇的訴訟を棄却しました。
【裁判・統計】裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第7回)について(裁判所ホームページ掲載)
平成29年7月に公表されたものですが、「迅速化」の標題とは別に、1審に要する期間や人証(尋問)の実施率など、「司法統計」として参考になるかと思います。
公表資料は、裁判所HPからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/hokoku_07_about/index.html
また、判例タイムズ1440号5頁以下にも掲載されています。
以下、何点か、参考事項です。
【全体について】
〇 民事第一審訴訟の新受件数は、14万8295件(うち4万7352件が過払金訴訟)(平成28年)
〇 民事第一審訴訟の新受件数は、過払金訴訟を除けば、ここ10年間、ほぼ9~10万件で推移している。
〇 民事第一審訴訟の平均審理期間は、8.6カ月(平成28年。過払金訴訟を除いても8.8カ月)
〇 人証調べ実施率は、14.6%、平均人証数は0.4(過払金訴訟以外では16.6%、0.4)
【建築関係について】
〇 建築関係訴訟の新受件数は、1969件(過払金訴訟除く全体の約2%)で、請負代金訴訟が1498件、建築瑕疵損害賠償訴訟が471件(平成28年)
〇 建築関係訴訟の平均審理期間は、18.8カ月で、請負代金訴訟が12.8カ月、建築瑕疵損害賠償訴訟(瑕疵主張あり)が24.3カ月(平成28年のまとめ)
〇 鑑定の実施率は、請負代金訴訟が0.4%、建築瑕疵損害賠償訴訟が2.3%(なお、民事第一審全体は0.5%)
〇 瑕疵主張ありの事案で付調停となると、平均審理期間は30・0カ月(瑕疵主張なしでも26・2カ月)
【裁判・刑事】いわゆる現金送付型の特殊詐欺事案において、受け子の詐欺の未必の故意、騙されたふり作戦の行われた受け子の共同正犯の成立を認めた裁判例(福岡高判H28・12・20)
判例時報2338号112頁に掲載されています。
上告されていますが、民事上の注意義務違反、ひいては被害者救済にも参考になる判示です。
【裁判・国家賠償】いわゆる過払訴訟における裁判官の貸金業者に対し同社に有利な偏頗的な釈明権を行使したことが違法とし、国家賠償を命じた裁判例(神戸地裁H28・2・23)
違法な釈明権行使を行った裁判官は、消費者側代理人退席後に、しかも別件事件について消滅時効の主張を促すなどの釈明権行使を行ったというもので、神戸地裁平成28年2月23日判決(判例時報2317号111頁)は、「民事訴訟の根幹に関わる当事者の平等取扱いに係る利益に対し、裁判官が職務上必要とする配慮を明らかに欠いたものといえるから、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認めうる特別の事情があるというべきである。」と述べ、国家賠償(5万5000円)を命じました。
本件のような違法な釈明権行使を行う裁判官の存在は司法へ信頼を根底から失わせ得るものであり、強い危機感を感じるところです。
【裁判・民事】温泉付きホテル内のマッサージ店で施術を受けた利用客の術後歩行障害等について、会社法9条の類推適用により、マッサージ店とは別法人のホテルの賠償責任を認めた裁判例(神戸地裁姫路支部H28・2・10)
会社法9条は、(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)として「自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定しており、かつて名板貸責任といわれていたものです。神戸地裁姫路支部平成28年2月10日(判例時報2318号142頁。金融商事判例1512号8頁)は同条の類推適用によってホテルの法的責任を認めたものです(賠償額約8727万円)。平成17年改正商法前の商法23条に同様の規定があり、最判平成7年11月30日もスーパーマーケット、同店内のペットショップの事案で、同条類推適用によってスーパーマーケットの責任を認めました。なお、最判昭和43年6月13日において営業は同種である必要があるとはされていますが、同種性は外観等から判断されるものと理解されています。
【裁判・民事】本訴請求債権が消滅時効したとされることを条件とする、反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することは許されるとする最高裁判例(H27・12・14)
本判断の前提となる問題点は、「係属中の別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、重複起訴を禁じた民訴法142条の趣旨に反し、許されない(最高裁昭和62年(オ)第1385号平成3年12月17日第三小法廷判決・民集45巻9号1435頁参照)。」との規定・判断ですが、最高裁平成27年12月14日判決(金融・商事判例1484号8頁)は、前記問題点の指摘に引き続き、「しかし、本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として、反訴において、当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許されると解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。」「時効により消滅し、履行の請求ができなくなった債権であっても、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、これを自働債権として相殺をすることができるところ、本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断される場合には、その判断を前提に、同時に審判される反訴において、当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権とする相殺の抗弁につき判断をしても、当該債権の存否に係る本訴における判断と矛盾抵触することはなく、審理が重複することもない。したがって、反訴において上記相殺の抗弁を主張することは、重複起訴を禁じた民訴法142条の趣旨に反するものとはいえない。このように解することは、民法508条が、時効により消滅した債権であっても、一定の場合にはこれを自働債権として相殺をすることができるとして、公平の見地から当事者の相殺に対する期待を保護することとした趣旨にもかなうものである。」と判示しました。
原審(東京高裁平成25年1月31日・金融商事判例1484号14頁)は相殺の審理・判断をしなかったようで最高裁で破棄差戻しとされました。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792