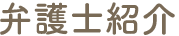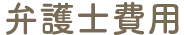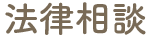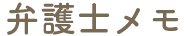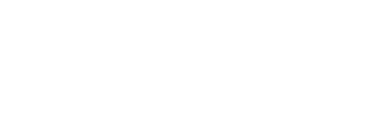
【裁判・民事】弁護士が不動産の売買による所有権移転登記手続について、売主側から依頼を受けていたところ、買主に対し、偽造された住民基本台帳カード等をもとに売主についての誤った本人確認情報を提供したことについて、弁護士の不法行為責任を認めた事例(東京地裁H28・11・29)
判例時報2343号78頁に掲載されています。
過失相殺が4割とされていますが、1億6000万円超の賠償が命じられています。
判決では、「証拠(乙2)によれば、自称Cが提出した本件遺産分割協議書の記載内容は、Iの死亡日が「平成44年9月17日」とされていること、相続開始日と被相続人の死亡日が異なっていること、上記相続開始日及び被相続人の死亡日がいずれも本件不動産の登記事項証明書に示された相続開始日(すなわち被相続人の死亡日)と異なっているという明らかに誤った内容を含むものであり(認定事実(11)エ)、遺産分割協議の内容を正確に示すものではなく、そのままでは遺産分割協議に基づく登記申請に用いることができないことを容易に気付くことができる内容のものである。」とされています。
事案としては賠償を命じられるものと思いますが、弁護士業務遂行として留意すべき事項も少なくいないと思われます。
【裁判・相続】秘密証書遺言を遺言能力を欠くとして無効とした事例(東京地裁H29・4・25)
判例時報2354号50頁に掲載されています。
遺言作成時に80歳を超えておりm18億円を超える財産に関し複雑な内容となっていたようで、裁判上の鑑定が実施され、遺言能力が否定された事案です。秘密証書遺言の形式がとられることは実務上多くはありませんが、遺言能力の判断など参考になるものです(控訴されています)。
【裁判・相続】公正証書遺言につき、遺言者が遺言内容を具体的に語ることをしなかったことから、口授の要件を備えていないとして、無効とした裁判例(東京高裁H27・8・27)
判例時報2352号61頁に掲載されています。
上告・上告受理申立も排斥され確定しています。これまでの判例(大判大7年3月9日・刑録24・197、最高裁昭和51年1月16日・裁判集民117・1)の流れに沿うものですが、近時の高裁判例としても参考になると思われます。
【裁判・相続】裁判所が民法941条1項(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)の規定に基づく財産分離を命じることができる場合を示した最高裁決定(H29・11・28)
民法941条1項は「相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。」と規定しているのみであるところ、最高裁平成29年11月28日決定(金融商事判例1532号8頁)は、「家庭裁判所は、相続人がその固有財産について債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから、相続財産と相続人の固有財産とが混同することによって相続債権者等がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難と認められる場合に、民法941条1項の規定に基づき、財産分離を命ずることができるものと解するのが相当である。」として同規定に基づき裁判所が財産分離を命じることができる場面(事案)を示しました。
相続の場面でよくある事案ではないですが、1・2審での判断が分かれていたこともあり、実務上、重要な判断と思われます。
【裁判・相続】被相続人の身の回りの世話をしてきた近隣在住の知人、被相続人の成年後見人(四親等の親族)について、特別縁故者として財産分与を認めた事例(大阪高裁H28・3・2)
大阪高裁平成28年3月2日決定(判例時報2310号85頁)は、原審を変更し、各人を特別縁故者と判断しました(確定)。
特別縁故者の規定は下記のとおりで、実務上、具体的判断の参考になると思われます。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)第九百五十八条の三
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
【裁判・相続】共同相続された普通預金債権、通常預金債権、定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく、遺産分割の対象となるとする最高裁決定(H28・12・19)
可分債権は相続分に応じて取得するとしてきた最高裁昭和29年4月8日判決(判例タイムズ40号20頁)や実務上の取り扱いを変更するもので、「画期的という以上の、激震を走らせるような大法廷の決定である。」(最高裁平成28年12月19日大法廷決定を掲載する金融・商事判例1508号10頁以下の解説コメント)といわれるものです。
現在の最高裁の考える遺産分割のあり方を示すもので、実務上は大きな影響あるものです。
判決全文・裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf
【裁判・相続】いわゆる花押は自筆証書遺言(民法968条1項)の押印にはあたらないとした最高裁判例(H28・6・3)
最高裁平成28年6月3日第二小法廷(判例時報2311号13頁)は「花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。」と判示しました。
最高裁平成元年2月16日(民集43巻2号45頁)は、押印は指印をもって足りる旨述べていましたが、いわゆる花押は、サインや記号的なものといわれる一方、それらとは全く同じではないともいわれ、概念自体が不明確なものでもあり、「我が国において、印章に押印に代えて花押を書くことによって文章を完成させる慣行ないし法意識が存するものとは認め難い」として、異なる扱いになったものと思われます。
実務上重要な判断でありますが、事案としては、死因贈与の有効性について審理を原審(福岡高裁)に差し戻している点も留意が必要かとは思われます。
【裁判・相続】民法910条(相続の開始後に認知された者の価額支払請求権)の価額算定時期、履行遅滞時期を示した最高裁判例(H28・2・26)
最高裁平成28年2月26日判決(第二小法廷。下記裁判所HP、判例時報2301号92頁)は、(1)相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は、価額の支払を請求した時であること、(2)民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は、履行の請求を受けた時に遅滞に陥ることを明確にしました。
事案としては必ずしも多いものではありませんが、これまで明確となっていなかった点を明らかにするもので、実務上も重要な意味を有するものです。
判決文・最高裁HP http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85705
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
【裁判・家族】公正証書遺言を遺言能力を欠き無効とした裁判例(東京高裁H25・8・28)
死亡6日前に作成された公正証書遺言の有効性が争われた事案で、東京高裁平成25年8月28日判決(判例タイムズ1419号173頁)は、公正証書遺言を無効としました(確定)。若干前の判決ですが、公正証書遺言が無効とされる事案として、実務上参考になると思われます。以下、判示内容を抜粋します。
「前記認定事実によれば、確かに、被相続人は、遺言する意思を有し、自己の遺産の配分等について、遅くとも平成22年1月ころより検討していたことが認められる。しかしながら、被相続人は、進行癌による疼痛緩和のため、同年2月末ごろから、慶應義塾大学病院より麻薬鎮痛薬を処方されるようになり、同年7月23日に同病院に入院した後は、せん妄状態と断定できるかどうかはともかく、上記の薬剤の影響と思われる傾眠傾向や精神症状が頻繁に見られるようになった。そして、本件遺言公正証書作成時の被相続人の状況も、公証人の問いかけ等に受動的に反応するだけであり、公証人の案文読み上げ中に目を閉じてしまったりしたほか、自分の年齢を間違えて言ったり、不動産を誰に与えるかについて答えられないなど、上記の症状と同様のものが見受けられた。加えて、本件遺言の内容は、平成22年1月時点での被相続人の考えに近いところ、被相続人は、同年7月に上記考えを大幅に変更しているにもかかわらず、何故、同年1月時点の考え方に沿った本件遺言をしたのかについて合理的な理由は見出しがたい。」「以上のような本件遺言公正証書作成時ころの被相続人の精神症状、同公正証書作成時の被相続人の態様及び合理的な理由がないにもかかわらず、被相続人の直近の意思と異なる本件遺言が作成されていることに鑑みると、被相続人は、本件遺言公正証書作成時に遺言能力を欠いていたと認めるのが相当である。」
【裁判・家族】被相続人の相続財産総額約1億4000万円の預金につき、生前や死後の縁故の程度に応じて、義理の姪に500万円、義理の従妹に2500万円を分与した裁判例(東京家裁H24・4・20)
相続人が不存在の場合には、被相続人と特別の関係にあった特別縁故者からの請求によって、その者らへ相続財産の分与がなされ得ますが(下記民法958条の3)、本件東京家裁平成24年4月20日(判例時報2275号106頁。確定)は、その具体的適用事例です。
特別縁故者の事例は、内縁の妻や事実上の養子の事例が多いと言われますが、本件は、義理の姪は3親等、義理の従妹は4親等になり、適用事例・基準として参考となるものと思われます。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792