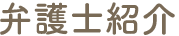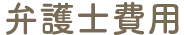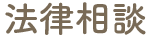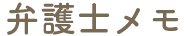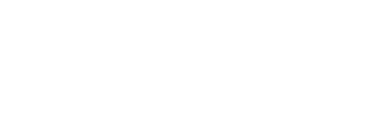
【裁判・消費者】時効完成後の支払(継続)について、時効援用は信義則に反しないとして債務消滅を認めた裁判例(名古屋簡裁H29・7・11、福岡簡裁H29・7・18)
いずれも消費者法ニュース113号217頁、219頁に掲載されています。
時効完成後の支払いについては、業者側から、最高裁昭和41年4月20日判決があり信義則に反し援用できないと判例が引用されますが、同最判は、個別事案の判断であり(とくに債務者から支払いを積極的に申し出ていたもの)、当然、全ての事案においては時効援用が信義則に反するわけではありません。名古屋簡裁の事案は和解契約書も作成されていたもの、福岡簡裁の事案は40回もの支払いが存したものですが、いずれも、個別具体的事情を踏まえ、時効援用・債務消滅を認めたものです。
実務上、被害救済に大いに参考になるものと思われます。
【裁判・国家賠償】いわゆる過払訴訟における裁判官の貸金業者に対し同社に有利な偏頗的な釈明権を行使したことが違法とし、国家賠償を命じた裁判例(神戸地裁H28・2・23)
違法な釈明権行使を行った裁判官は、消費者側代理人退席後に、しかも別件事件について消滅時効の主張を促すなどの釈明権行使を行ったというもので、神戸地裁平成28年2月23日判決(判例時報2317号111頁)は、「民事訴訟の根幹に関わる当事者の平等取扱いに係る利益に対し、裁判官が職務上必要とする配慮を明らかに欠いたものといえるから、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認めうる特別の事情があるというべきである。」と述べ、国家賠償(5万5000円)を命じました。
本件のような違法な釈明権行使を行う裁判官の存在は司法へ信頼を根底から失わせ得るものであり、強い危機感を感じるところです。
【裁判・民事】本訴請求債権が消滅時効したとされることを条件とする、反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することは許されるとする最高裁判例(H27・12・14)
本判断の前提となる問題点は、「係属中の別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、重複起訴を禁じた民訴法142条の趣旨に反し、許されない(最高裁昭和62年(オ)第1385号平成3年12月17日第三小法廷判決・民集45巻9号1435頁参照)。」との規定・判断ですが、最高裁平成27年12月14日判決(金融・商事判例1484号8頁)は、前記問題点の指摘に引き続き、「しかし、本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として、反訴において、当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許されると解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。」「時効により消滅し、履行の請求ができなくなった債権であっても、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、これを自働債権として相殺をすることができるところ、本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断される場合には、その判断を前提に、同時に審判される反訴において、当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権とする相殺の抗弁につき判断をしても、当該債権の存否に係る本訴における判断と矛盾抵触することはなく、審理が重複することもない。したがって、反訴において上記相殺の抗弁を主張することは、重複起訴を禁じた民訴法142条の趣旨に反するものとはいえない。このように解することは、民法508条が、時効により消滅した債権であっても、一定の場合にはこれを自働債権として相殺をすることができるとして、公平の見地から当事者の相殺に対する期待を保護することとした趣旨にもかなうものである。」と判示しました。
原審(東京高裁平成25年1月31日・金融商事判例1484号14頁)は相殺の審理・判断をしなかったようで最高裁で破棄差戻しとされました。
【裁判・民事】債務整理を司法書士に依頼した債務者(借主)から、委任後に時効期間が完成し消滅時効を援用した事案につき、援用行為が信義則に違反するとまではいないとして時効消滅を肯定した裁判例(東京地裁H25・6・10)
東京地判平成25年6月10日(判タ1415号298頁)は、貸金業者としては訴え提起による時効中断が可能であったこと等を指摘し、司法書士の対応に不誠実な点がみられるにせよ、債務者(借主)の消滅時効援用行為に信義則に反するものとまでいうことはできないとして債務消滅を認めました(原審東京簡裁平成24年1月9日判決を破棄し自判したもので確定しています)。
債務整理の実務上も重要な事例と思われます。本件の貸金業者は、株式会社オリエントコーポレーションです。
なお、消滅時効の事案では、債務者(借主)の時効完成後の返済などがあると、業者(貸主)側から、最判昭和41年4月20日(民集20巻4号702頁)を引用して『援用は信義則違反』と主張されることがありますが、同判決は、債務者(借主)が債務存在を認めたのみならず積極的に具体的返済計画等の申し入れを行っていた事案であるなど個別具体的な事実関係に基づく判断ですから、現在の、貸金業者・消費者という関係に一般的に妥当するものではない点などは注意が必要です。
【裁判・民事】主債務が、再生債権として異議なく確定し、再生計画認可決定も確定した場合に、その連帯保証債務の消滅時効期間も10年に延長されるとした裁判例(東京地裁H26・7・28)
東京地判平成26年7月28日(判タ1415号277頁)は、この場合の主債務については民法174条の2第1項により時効期間が10年となることを前提に、連帯保証債務も、民法457条1項にあらわれるところの消滅時効制度の適用場面における保証債務の附従性から延長の効果を生じ、消滅時効期間は10年となると判示しました。
最判昭和43年10月17日(判タ228号100頁、判時540号34頁)は、主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が民法174条ノ2の規定によって10年に延長される場合には、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく10年に変ずるものと解するのが相当である旨判示していますので、民事再生の場面における確認的な裁判例ですが、時効問題は実務上重要ですので、参考になると思われます。
関係条文は以下のとおりです。
(判決で確定した権利の消滅時効)
174条の2 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第457条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
【裁判・民事】特定調停における清算条項は、過払金返還請求権を失わせるものではないとする最高裁判例(H27・9・15)
原審(東京高裁)が、特定調停における清算条項を公序良俗違反として消費者救済を図っていましたが、最高裁H27・9・15は、特定調停は債務支払協議のための手続きであることから、清算条項が存するとしも、いわゆる過払金還請求権を失わせるものではないとして、調停の有効性を前提としつつ限定的ですが過払消返還請求の余地を残しました(実際には時効等も問題も生じ得るものです)。
【裁判・民事】事故後26年以上経過した後に提起された損害賠償請求訴訟において、民法724条に基づく消滅時効・除斥期間の主張を排斥した裁判例(東京地裁H26・4・14)
東京地裁平成26年4月14日判決(判例時報2233号123頁)は、鉄道高架橋のブロック片落下事故によって頭部を受傷した被害者が、相当期間経過後に知的障害・高次脳機能障害等が発生したとして事故後26年以上経過した後に損賠賠償を求めた事案において、民法724条前段については「被害者がその請求権を行使することができる程度に具体的な認識が必要」として、民法724条後段については「損害の性質上加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が生じる場合」として、いずれも加害者側の主張を排斥し、1億5884万円超の損害賠償を命じました(控訴あり)。
民法724条後段を古典的な除斥期間と把握していると思われる点は問題ですが、その除斥期間の不合理性を乗り越える事案として、実務上、参考になるものです。
【裁判・行政】道路法による市道認定なき土地(法定外公共財産)につき、公物であることから取得時効を認めなかった裁判例(東京高裁H26・5・28)
公物に対する時効取得は、原則認められないとされ、長年公共の用に供されなかったなど公用廃止がなされたと評価できる場合に限って私人による時効取得が認められるとされてきました(最高裁昭和51年12月24日判決・判例時報840号55頁)。東京高裁平成26年5月28日判決(判例時報2227号37頁)も、その最高裁判例に反するものではありませんが、最高裁判例後の数少ない事案として参考になると思われます。(上告等がなされています。)
【裁判・民事】後見開始決定前であっても、未成年者又は成年被後見人に関する時効停止を認める民法158条1項の類推適用を認めた最高裁判例(H26・3・14)
最高裁平成26年3月14日判決(判例時報2224号44頁)は、「時効の期間満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも、時効期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がなされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その者に対して、時効は、完成しないと解するのが相当である。」と判示しました。
似た事案の最高裁の判断(平成10年6月12日・判例時報1644号42頁)の流れに沿うものですが、はじめての判断であること、時効期間経過前の審判申立てが必要とされていること、さらに、後見人に就職した場合の援用権行使期間など、実務上、留意すべきものと思われます。
【裁判・時効】交通事故から20年経過後に提起された損害賠償請求につき、民法724条後段(20年の除斥期間)の適用はないとした裁判例(水戸地裁下妻支部H25・10・11)
水戸地裁下妻支部平成25年10月11日判決(判例時報2222号83頁)は、「原告が症状固定の診断書を被告側任意保険会社に提出して事前認定の手続を進めさせてから平成25年2月23日に本訴を提起するまでの経過は、原告が本件交通事故による損害賠償請求権を行使する一連一体の行為と捉えることができ、そうすると、本件では本件交通事故から20年の除斥期間内において権利行使がなされたと見るのが相当であるから、これによって除斥期間の満了は阻止されたことになると解するのが相当である。」「本件では民法724条後段の適用はない。」と判示しました。
民法724条後段を古典的な除斥期間と解する見解はもはや少数派と言われていますが、この点をおくとしても、本件は個別具体的な被害実態及び事実経過に鑑み、被害救済の途を開く参考となるものです(なお、控訴されています)。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792